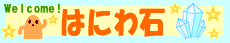恒星ぱらん見てみました
ドタバタし通しでしたが、うわさの恒星パランについて、やっと自分のを見てみました。
詳しくは、松村潔著「トランシット占星術」をご覧ください。
自分の生まれた日の惑星がアングル(ASCとかMCとか)に位置したときに、同時にアングルにひっかかっている恒星があったとき、それをパランというそうです。
惑星同士であっても、パランと呼ぶようです。
オーブ0.5で見てみたら、私の場合、お誕生日の太陽が、東の地平線にきていたとき(つまり日の出)、ラス・アルゲティという恒星が天頂にありました。
ラス・アルゲティは自然崇拝とか、崩れているものを矯正しようとするという意味があるそうです。
地平線から天頂までの間が表す、若い頃に、そういうものに関連するという風に読むようです。
前世を表すという月のパランは、ルクバトという恒星でした。粘り強いらしいです。首尾一貫とか、安定性という意味があるそうです。
今の私の年代は天頂にあたり、月はルクバトで、他に水星がラス・アルゲティ、木星がラス・アルハゲという、癒しとか修正、セラピーみたいな意味の恒星とパランでした。
なるほどーという感じです。縄文やアニミズムとか、古代の霊魂観みたいなのに長々と取り組んでいるのも納得ですね。
人生の秋を迎えるまでの間は、そういう知識とか、安らぎみたいなものと関連していくことになるようです。
アングルやホロスコープは、春分、夏至、秋分、冬至にも当てはまります。
春分は東の地平線(ASC)、夏至は天頂(MC)、秋分は西の地平線(DSC)、冬至は天低(IC)です。
私のたまふりの講座では、これらの流れを、月の満ち欠けでも説明したりします。
冬至は新月にあたり、夏至が満月です。半月は陰陽中和でそれぞれ春分、秋分に当てはまります。
このサイクルは、死と再生、世の中に出て行くとき、最も満ちるとき、引退の時期、そしてまた死に向かうという繰り返しです。
冬至には、死と再生と言う意味がありますが、その一方で、春分も誕生の象徴だったりします。
それについて、以前、松村先生に問い合わせたことがあるのですが、冬至が死で、春分が誕生というわけでもなく、サイクルの中に、死んでいる時間というのは存在しないということでした。
パランの影響を見るときは、東の地平線から天頂までの期間は0~20才頃ということですが、天低が冬至に対応するならば、そこが死と再生であっても良いのではないかとも思いました。
あるいは、冬至点(天低)から春分点(東の地平線)まではミタマノフユで、胎児のように、生きているのか、霊魂なのか、あるいは生まれて間もない子のように、まだ確実な形や生命力を持たないものが、静かに力を蓄えるというそのままの意味で良いのかなとも思ったり。
本の中にある、ヒンドゥーの四住期では、天低は死であり、再生ではないということですが、しかし、やはり冬至点たる天低こそ死と再生であり、春分点である東の地平線は学生とか社会人デビューとか、世の中に出て行く時期にあたるというのが、私的に一番しっくりきます。
春の訪れまでの冬の間は、ミタマノフユといって、この世に出てくるための霊魂、霊的な力を溜め込む時期であるとされ、諏訪大社などの神社祭祀でも、祭神となる蛇神役が御室にこもり、しばらくした後に長く成長した姿に変化して出てくるというのがあります。
西洋占星術は、生まれた瞬間の天体配置をそのまま生のまま書き表したもので、東洋占星術にくらべ、かなりナチュラルな印象で、読み手によって色々な解釈ができるのが魅力だったりします。
恒星パランも、天空の星空をそのまま見ているような感じで、結構好きかもです。
身近な人たちのパランも見てみたいです。