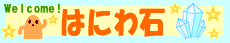食葬
両親がアメリカから戻ってきました。視察兼観光みたいなよくわかんない旅行ですが楽しかったそうで良かったです。
母は初めて見るアメリカの風景に感動していました。グランドキャニオンに行ってきたとか。
仕事のついでで、アメリカの国立公園は大体行ったのですが、やはり中西部は素晴らしいです。アーチーズとかホワイトサンズとか、感動するしかないです。セドナも好きかも。
いつか親を連れて中西部あたりを巡りたいです。運転できないけど。
お土産はコーチのバッグでした。この前違うのを弟に貰ったので、ブランドバッグはこれで2個目です。自分じゃ絶対買わないという。
最近、少し料理をするようになって、結構楽しいです。
母が嫌々家事をやってるのを見てきたせいか、すごく嫌なイメージがあったのですが、やってみるとそんなに苦ではなく、むしろ料理が上手にできたときの快感がすごいです。
いかに冷蔵庫の中身を組み合わせるか考えるのも楽しいです。
蟹座金星が活発化してるのかしら。
そういえば、食葬というのがあって、昔は亡くなった人の肉を食べてました。
我々は日頃から食べ物の命や魂(ウカノミタマ)を頂いて生きてるわけですが、食葬では、そうして、故人の魂を取り込むのです。
沖縄のほうの島では、比較的近年まで行われてたみたいです。
親族には赤肉、遠い親戚には脂肪が割り当てられました。
以前、講座でもよく説明していましたが、戦で死んだ人の肉も食べていたようです。
荒ぶる魂を取り込むことに意味があったともされてます。
でも、もしかしたら、食糧不足の時代においては、食料の一環としての意味もあったのかもしれないなと思います。
縄文の貝塚からは、貝なんかのゴミと一緒に人骨も出てます。
一部のインテリが埋葬を始める以前には、他の食べ物のゴミと区別せず、食べた後に捨ててた可能性があります。
世界大戦中も、戦地の食糧不足の際には、死んだ仲間の肉を食べたりしてたそうです。
太ももとかだと、他の部位に比べ、抵抗なく食べられるとか。
世界の人口が70億を超えたといいますが、もしこのまま増え続けたら、食べ物がなくなって、共食いをする時代がくるのでしょうか。
そういえば、子供の頃に、昔はやっていたというノストラダムスの本が家の倉庫にあって、その中に、大きい7が小さい7になるという予言があったのを記憶しています。
人口70億が一気に減るなんて事があるかどうかわかんないけど、ちょっと怖いです。
でも、魂を取り込むという意味でいえば、食葬と臓器移植って似てるのかも。
どちらも、誰かの血や肉、骨の一部になるわけです。輸血も同じですね。
実際、臓器を移植したら、趣味や嗜好などが、以前の臓器の持ち主と同じものに変わったという例を聞きます。
また、亡くなった人の一部が、誰かの中で生き続けることができるというのは、遺族にとっては救われる部分があるそうです。
ドナーカードは持ってるけど、私の角膜は多分傷だらけで使い物にならなそうです(笑)
霊能者の角膜を移植したら、なんか不思議なもの見えたりして。
輸血をしてはいけない宗教というのもありますが、医療が発達していない時代において、血液型の違いによって死亡例があったり、病気の感染があったりという事例が、危険視されたからなのかなと思ったり。
これはちょっと関係ないけど中世の頃には血を抜くと元気になるとかいう医療行為もあったようです。
輸血禁止というのは、国家とか律令体制が整っていない時代の法律みたいな役割もあった宗教の教えが、今にそのまま伝わってしまってる部分もあるのかもしれません。
実際は、若い人の血を老人に輸血すると、老人特有の症状が改善することが分かっているようです。
血には霊(チ)が宿るといわれますが、若くてエネルギーに満ち溢れた霊魂を分けてもらうことにもなる気がします。