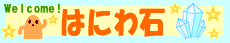大学に行って来ました
16日に、聴講生として講義に初参加してきました。
2時間目から7時間目まで、フルに入れていたのですが、思っていたよりも大変でした。
最初はやる気満々で席に着くものの、日ごろの睡眠不足や疲れもあり、だんだん講義の声が子守唄になり、なんとか目を開けているのが精一杯です。
7時間目にもなると、ノートの字が解読不能になります。せっかく、賀茂神社についての講義だったのに、もったいないったらありません。
これからは、前日にはきちんと睡眠をとってから行くことにしました。
翌日が合格発表だったのですが、色々忙しくてなかなか行けず、19日に再び学校に行ってきました。
おもてに貼り出されておらず、直接聞きに行こうと思ったら、ちょうど昼休みに入っており、1時間近く待つ事になってしまいました。
図書館と近くの公園で時間をつぶした後、振込用紙と簡単な説明だけ渡されたのですが、これだったら、郵送してくれれば良かったのに、という感じでした。
良く考えたら、牡牛座のロングボイドの時間帯だったのでした。
学生証は、次回の講義の際の受け取りで、かえって良かったです。
ボイドは、うっかりミスとか、契約ミス、その時間の間に決めたことや始めたことが無駄になるという作用があります。
天中殺なんかは気にならないけれど、私のようなうっかり者にとって、ボイドは本当に要注意です。
こんど、ボイドタイムのページでも作っておこうかと思っています。
さて、肝心の講義の内容は、月曜の初回だったためか、単位のとり方とかテストの説明なんかが多かったのですが、それでも、色々面白いものがありました。
なかでも、1時間目の伝承文学の講座は、ちょうど気になっていたテーマで、とても面白かったです(1時間目はしっかり起きていられました笑)。
桜はサ(稲魂)クラ(座)で、田の神が宿っているという意味がありますが、日本人がどうして桜を愛するのか、そもそもどうして桜が田の神様に関係するようになったのか、という、長年の謎が解けて、嬉しくなりました。
万葉集などで、桜が散るのを惜しむ歌が繰り返されるのは、奈良時代以前から、村の運命を占う木として使われていたからで、満開で長持ちは吉兆、早く散るのは凶兆だったのだそうです。
どうして桜が田の神かというと、花びらを米に見立てていたのだそうです。
満開の桜は、昔の人にとっては大きな米俵のように見えていたのかもしれません。
実際の授業に参加してみて驚いたのは、意外と人が多いという事で、比較的広い教室でも、結構いっぱいでした。
単位の説明があったせいかもしれないですが、携帯をいじくる人も少なく、思っていたより結構まじめな感じで、ちょっとびっくりしました。
ひとつ休講があったので、学食でカレーを食べる事ができ、大学生気分が味わえたのも、ちょっぴり嬉しかったです。