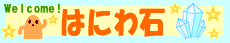石と魂
最近、毎週月曜日は大学に行き、一日中勉強しているのですが、昔の人の霊魂観を学ぶのが本当に楽しくて仕方がないです。
そもそもこういう事を、大学で学べるということ自体も面白いです。
昨今のスピリチュアルブームで、霊魂がテーマのテレビ番組も増え、魂の事を考える機会が以前よりは増えたと思うのですが、だんだん昔の日本人の考え方に近づいてきたというか、先祖がえりのように感じられます。
古来日本では、スピリチュアルな物事に対する考えや接し方は、今のように、特別視されるものではなく、ごく自然に日常生活に溶け込んでいました。
源氏物語なんかもそうですが、昔の人の事を理解するには、魂の概念が、本当に重要です。
魂はタマであり、玉、つまり石にとても関係します。
よく、石は念が入って云々といいますが、それは、持ち主の魂の一部がそこに宿るという事なのです。
だから、お守りとしてはもちろんですが、強いプラスの念(具体的なビジョン、例えば手に入れたいものや将来イメージ)を込めれば、それをかなえる助けになると言えます。
石の属性や種類を理解してきちんと選べば、それは、さらに強く作用すると思います。
また、もちろんサイズにもよりますが、石は、いわゆる、神様というか、高い次元のものが降りてくる接点にもなったりします。
注連縄をつけられた岩や要石というのは良く神社でも見かけますね。
墓石なんかも今は飾り物のような感じになっていますが、元々は霊魂にとっての現世との接点や依代みたいなものではないかと思います。
そんな風に、しばらく学んでいて、昔の豪族がなぜ勾玉をあんなに身に着けていたのか、なぜその必要があったのか、そしてそれはどこから来たのかも、最近、自分なりにですが、より深いところまで理解できた気がします。
例えば、王という字は、天と地の中間にいる人を示していて、天の意志を地につなぐ役割を表しているといわれています。
私は、それに加えて、より高い所にある、大いなる魂を一旦自らに定着させるという意味もあったのではないかと考えています。
神宮皇后と武内宿禰の逸話でも知られるように、昔は、王、巫女的要素を持つ、上に立つ者が神がかって語る言葉を、さらに審神者(さにわ)が解読し、伝えていました。
そうすると、もしかしたら、王という字は、限りなく続く上から下への連鎖を簡略化したものかもしれないな、と思ったりもします。
ともかく、上に立つ人間には、そうした能力に加え、魂の大きさと、それを宿らせるだけの度量が必要とされていたのではないでしょうか。
そして、その力を増すためにも石が使われたのではないかと考えています。
また、身に着けていた勾玉は、忠誠を誓った部下から分霊の意味を込めて送られたものかもしれません。
ちなみに、お中元、お歳暮などは、もともと相手に魂を分けるという考えから来ているのは、今となっては、ほとんど知られていませんが、心を送るという意味合いは、今でも生きているといえます。
話が横にずれましたが、昔の人の石の使い方を考えていて、神道では魂振り、魂鎮めというのですが、魂を体に定着させる為のおまじないや、人に魂を分けるという考え方やおまじないなど、そういったものをプラスして、実際試してみると、思っても見ないような効果があったりと、とても面白いです。
本当に、物は使いようです。
特に、精神が不安定な人や、影響されやすく自分を見失いがちな人の場合は、石を自分の魂の拠り所として使うことで、ずいぶんと違ってくるようです。