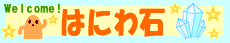両面はにわ
和歌山の岩橋千塚古墳の大日山35号墳(六世紀前半)で、両面のハニワが発掘されました。
片側は目が釣りあがっていて、もう片側は柔和な顔です。
今のところ、古墳を守るハニワであるとか、内と外を表しているのではないかという説があるようです。
この古墳は、古代豪族の紀氏が造営したものとされています。
紀氏は、武内宿禰の直系の子孫です。
武内宿禰といえば、神功皇后の審神者であり、優れた神通力を持つ人物として知られ、「両面宿禰」といって、二つの顔を持つ像が知られています。(ちなみに、宿禰というのは、魂が宿る人と言う意味です)
一説には、宿禰は、資源を求めて、日本海側から朝鮮半島に渡った人々の子孫で、再び日本に戻ってきた人物とされています(天日矛やツヌガアラシトと同じ人物と言う説もあります)。
つまり、両面というのは、朝鮮半島と日本の二つの属性を表しているという事になります。
今回見つかった両面ハニワは、片面が目の釣りあがった大陸型(弥生人)の顔つきであり、この説を裏付けるもののような気がしてなりません。
昨日の日記で大国主について少し触れたのですが、私は武内宿禰が大国主のモデルで、また、神功皇后は賀茂神社に祭られている玉依姫と同一ではないかと考えています。
また、修験道は役小角といい、賀茂建角身尊といい、角に関連が多く、先ほど書いたように宿禰はツヌガアラシト(角がある人の意味)と同一とされ、子孫には木角宿禰がいたり、もしかしたらこの人こそ賀茂建角身尊ではないかと思っています。
書き始めるときりが無いので、また歴史のページにまとめたいと思っています。
片側は目が釣りあがっていて、もう片側は柔和な顔です。
今のところ、古墳を守るハニワであるとか、内と外を表しているのではないかという説があるようです。
この古墳は、古代豪族の紀氏が造営したものとされています。
紀氏は、武内宿禰の直系の子孫です。
武内宿禰といえば、神功皇后の審神者であり、優れた神通力を持つ人物として知られ、「両面宿禰」といって、二つの顔を持つ像が知られています。(ちなみに、宿禰というのは、魂が宿る人と言う意味です)
一説には、宿禰は、資源を求めて、日本海側から朝鮮半島に渡った人々の子孫で、再び日本に戻ってきた人物とされています(天日矛やツヌガアラシトと同じ人物と言う説もあります)。
つまり、両面というのは、朝鮮半島と日本の二つの属性を表しているという事になります。
今回見つかった両面ハニワは、片面が目の釣りあがった大陸型(弥生人)の顔つきであり、この説を裏付けるもののような気がしてなりません。
昨日の日記で大国主について少し触れたのですが、私は武内宿禰が大国主のモデルで、また、神功皇后は賀茂神社に祭られている玉依姫と同一ではないかと考えています。
また、修験道は役小角といい、賀茂建角身尊といい、角に関連が多く、先ほど書いたように宿禰はツヌガアラシト(角がある人の意味)と同一とされ、子孫には木角宿禰がいたり、もしかしたらこの人こそ賀茂建角身尊ではないかと思っています。
書き始めるときりが無いので、また歴史のページにまとめたいと思っています。