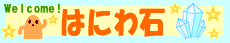シンポをはしご☆

写真は、ちょっと成長した、くるみたんです。もう4ヶ月になりました。
お客様から可愛いお洋服やハーネスを頂いてしまいました。
胴が長いので、半分背中が出てるのですが、良く似合っています。
くるみは、顔を含めて、全体的にパーツが長めで、ちょっと都会的な雰囲気というか、水瓶座体型な感じです。どちらかというと、お父さん犬似かも。
母犬は、顔がまん丸でどっしり感があります。
この前、2つの大学のシンポジウムをハシゴしてきました。
結構、興味のあるものがだぶってたりする事があって、困るのですが、そんなに離れてないというのと、知り合いの方がご一緒くださったので、頑張って行ってきました。
片方は、民俗とか文学、映像などから、渋谷を読み解くというような内容でした。
田山花袋の「少女病」からの引用が強烈で、明治の昔から、電車の痴漢予備軍みたいなのがいたんだなとびっくりしました。でもちょっと続きが気になる感じで、読んでみたいです。
切れ目で退席して、次の大学に向かったのですが、それなりに離れてて、到着したのはほとんど終わり際に近かったですが、無縁社会と宗教者という内容で、色々な試みについて紹介されてたり、面白かったです。
お世話になっている先生が司会をしていて、終わってからご挨拶も出来たのでよかったです。
神社とか、お寺の講とかは逢引きや男女の出会いの場所として使われてた歴史がありますが、今は、地域の人との関わりとかの、重要なポイントになりうるようです。
実際、私の知っている宗教団体の、自宅での集まりなどを見ていると、濃厚かつ密接な人とのかかわりがあり、無縁に近くなってしまったお年寄りなんかは、それによってずいぶんと助けられてるようにも見えます。
多分、そういった集まりに関わっていることで、知らない間に白骨化していたというようなことは起きにくい気がします。
宗教だけではなく、趣味の集まりとかでも良いのだとは思いますが。
神社のお祭とかお寺の講とか、宗教者が積極的に活動して、人との輪を作り出すというのは、昔の日本の良さみたいなものが戻ってくる気がします。
小さい神社のお祭にいくと、地元のお年寄りとか、地域の人たちとの優しいふれあいがあったりして、思っていた以上に癒されたりするものです。
最近、人に勧められて「逝きし世の面影」という本を読んでいるのですが、江戸明治の頃には自称無宗教の人も多く、それでいて、人々がお祭に積極的に参加したり、人とのつながりがあった様子が描かれていて、なんだか、現代の試みに繋がるものを感じました。
さてさて、話は変わって、新たに講座案内を出させていただきました。
3月12日土曜日の午後2時から、西洋占星術基礎講座の第1回をやります。
決めるのが遅くなって、すみませんでした。
これ以降の4回は、参加者の方同士のすり合わせで決めていきたいと思っています。
あと、3月20日には、玉依姫ワークをやります。
この前、玉依姫命神社に行き、せっかく記事を書いたところで、巫女などにフォーカスしたお話が出来ればと考えています。
もちろん普段のたまふりと同様に、男性の方のご参加もお待ちしています。
またしても、千葉のど田舎でやるのですが、興味のある方は、ぜひご参加いただけましたら幸いです。