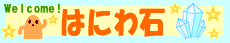歴博行ってきた

先日、佐倉の歴史民俗博物館に行ってきました。
民俗学コーナーのみ、改装のため結構長い期間閉まっていたのですが、ついに先月リニューアルオープンしました。
はやる気持ちを抑えて、せっかくなので他の展示もじっくり見てきました。
土偶とか骨格標本、遺跡から出土した様々な遺物など、いつもながら充実した品揃えで、楽しめました。
最近は漫画「へうげもの」のおかげで戦国時代末期にも興味が出てきて、その時代の街並みのジオラマとか遺物もじっくり堪能してきました。
茶の湯の展示がなかったのが寂しかったです。コーナー増設してほしいです。
へうげものはフィクションだけど、史実に基づいている部分も多く、千利休はただの茶人ではなく、政治への影響力もあったようです。
戦国時代の茶の湯文化は本当に面白いです。この前ついに茶の湯の本まで買ってきてしまいました。
茶道はやったことないので、そのうち機会があったらチャレンジしてみたいです。
さて、いよいよ民俗学コーナーに行ってみてびっくり。
壁一面にデパートのお節が並んでいました。あと鏡餅とか。何の説明もなくいきなり。
日本の重要な民俗ですが、お節や正月についての解説があっても良いのかもしれないと思いました。
あと、お土産文化として、各地のお土産が並んでいました。
こういうのは、外国人には受けるかもしれません。
ほかにも、サプリとか育毛剤とか、そこらへんの薬局で取り扱っている商品が沢山並んでいました。民俗学コーナーの展示物にしては最近過ぎるような感じで拍子抜けでした。
改装前みたいに、大正、昭和の古い薬とかだと面白いんですけど。
ほかに、折口とか柳田についての説明がすこしだけありました。
秋田の「鹿島様」の巨大な藁人形がどうなったのか気になったのですが、また違った藁人形の神様になっていました。
河童や妖怪についてや、地方の祭壇、東北の民家など、ちょっと新しいコーナーが増えていました。
個人的には、比婆荒神神楽のコーナーの、巨大な藁の龍や、切り絵が素晴らしかったです。
その後、近代や戦争のコーナーへ。心も体もずんと重くなるけど、見てきました。
あの時代に生きていた人はほんとうにすごいと思いました。
見てるだけで胸がぎゅっと苦しくなります。。
あと、博物館全般にいえるようですが、古いものが沢山あるからか、霊感のあるなしにかかわらず、結構色々影響を受けるようです。
特に戦時中の展示は、時代も近いから、色んなエネルギーが残っているような気がします。
ちなみに、画像は全然関係なく、学校の資料館の入り口の展示です。
面白かったのでアップしてみました。歴史民俗博物館と関係なくてすみません。
高句麗の遺跡から出た、これでもかといわんばかりに勾玉が無数にぶら下がった玉冠です。糸魚川産の翡翠は朝鮮半島に輸出されていて、とても珍重されました。
普段は被らなかっただろうけど、さぞかし重かっただろうなと思います。
これはレプリカだけど、勾玉は魂が籠もるので、実物はすごいパワーを発していそうです。
そういえば、新宿のミネラルフェアだったか、頭にハチマキのようにして沢山の勾玉を着けてるおじさんを見たことがあります。沢山の勾玉がぐるっと頭を取り巻いていて、首からも沢山提げていました。
よほど話しかけようか迷ったけど、勇気が出なくて、話しかけなかったことをあとで後悔しました。。
さて、明日はホロスコープブレス講座です。
一人ひとりのホロスコープに合わせてどうやって作るかレクチャーします。
寒い中来てくださる皆さんに楽しんでいただけるよう、頑張りたいです。
松村潔先生と共同開発の天然石グッズもそうですが、輪の形自体にすごく意味があるので、ブレスレットは開運グッズとしてはかなり使えるものだと思っています。