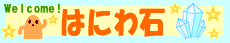古代史と占い
最近ものすごく暑いです。
それでも夜には少し涼しくなって、何とかクーラーが効くので、レポートをのんびりまとめています。
私のあまりにマニアックさに、学校の先生も興味を持ってくれて、ますますやる気が出てきます。
相変わらず豊受姫の事をやっているのですが、丹生都姫も賀茂の玉依姫も、豊受姫であるという結論以外に、調べている過程で色々な枝葉が出てくるので、そのうち、そういう事についてそれぞれレポートを書いても良いかな、なんて思ったりしています。
今は遠敷がもとは小丹生であることと、丹生都姫神社の共通点を書いています。
どちらも、神が害をなすという共通点があったり、若狭のお水送りと、丹生都姫の笑い祭りの起源が、神の集会への遅刻であるという共通点があります。
そういう細かい共通点から見えてくるものを探っていくのは、本当に楽しいです。
なんとなく、変な話、古代史と、占いというのは似たところがあって、関連性を見出して、答えを探すところが共通しているように感じます。
というのも、現代人は、物事の差異を見出すように意識が働くのですが、昔の人々は、物事を関連付けて考える習慣があったので、占いをやって、関連付けの訓練をしている人が古代史をやると、一層古代人に近づけたり、色んな発見があるかも、なんて思えます。
日本民俗学者の代表として、実証主義の柳田国男と直感の折口信夫というように、二人は対照的に、そして相互補完的に見られていますが、実はどちらも直感というのを大いに生かしていたのはよく知られています。
私はタロットは少し勉強した程度ですが、あのように、何枚ものカードを並べて、物事の関連性や推移などを読み取るという行為や、直感、深層意識を使うところなどは、古代人の考え方や物の感じ方に関係すると思うし、古代史研究にも役立つと感じます。
(占星術は理論占いなので、タロットと少し違うのです)
例えば、占いの歴史は相当古いですが、ウラという言葉自体が心という意味だとされています。(うら悲しいは、心悲しいという意味になります)
そうすると、ウラは浦であり裏なので、心の持つ、波立つもの、見えないもの、という意味が同時に共通して現れます。
そして、実際に、神話や伝説を見ていくと、古代の人々も、海や水を心や深層意識と結びつけて考えていたという事が分かります。
関連妄想的かな、と思うことも、後から調べると納得することが多いのも事実です。